羽生結弦、4Lz練習で負った怪我と復活への軌跡
羽生結弦選手は、難易度の高い4回転ルッツ(4Lz)の練習を行っている最中に、足首の捻挫や疲労骨折を経験しました。これらは何度も繰り返されるジャンプの着氷やエッジ操作によって引き起こされたものでした。それにもかかわらず、羽生選手は高い技術の習得を諦めず、専属の医療チームと共にリハビリを行い、競技への復帰を果たしました。本記事では、怪我の詳細、治療方法、再発防止策について詳述します。
4Lzトレーニングのリスクと影響
4回転ルッツは、踏切におけるエッジの角度が非常に特殊であり、助走からエッジを切り替える際に足首に大きな負担がかかります。羽生選手は練習中に繰り返し体重移動を行うことによって、靭帯へのストレスが蓄積されました。特に着氷時にハイエッジになると、内反捻挫のリスクが増し、常に捻挫の危険が伴う状況で練習をしていました。
2018年NHK杯前の怪我の経緯
2018年11月に行われたNHK杯の直前合宿で、羽生選手は4Lzの練習中に右足首を捻挫しました。アイスリンクでの激しい練習中に、足首の内側の靭帯を損傷し、歩行すら困難な状況になりました。大会本番では痛み止めを使用しながら演技を行いましたが、その後数週間は歩行やトレーニングが大幅に制限されてしまいました。
2019年シーズンの疲労骨折について
捻挫からの復帰後も4Lzの練習を続けた結果、2020年初めに足の甲に疲労骨折が見つかりました。レントゲンとMRI検査によって中足骨の微細骨折が確認され、「ハイリスクジャンプの練習が主な原因」と診断されました。そのため全日本選手権を欠場し、3か月間の完全安静と装具による固定治療が必要となりました。
専門医療チームによるリハビリ
羽生選手は所属するスポーツ医学センターとの連携を強化し、理学療法士やトレーナー、整形外科医からなる専門チームを編成しました。リハビリでは、筋膜リリースや超音波治療、低周波刺激療法を活用しながら、段階的な荷重訓練と可動域拡大の運動を行いました。5段階のリハビリを経て、約4カ月でリンクに復帰することができました。
練習メニューの見直しと怪我防止策
復帰後、羽生選手は4Lzの練習頻度を大幅に見直しました。毎日の練習を1~2回に制限し、週に1回はエッジワークやスピンを主体とした軽負荷セッションを取り入れました。ジャンプの負荷を軽減する代わりに、プライオメトリクストレーニングを行い、筋力と腱の弾性を強化しました。また、オフアイスではアキレス腱のストレッチやバランストレーニングにも重点を置き、再発のリスクを低下させました。
メンタルケアとモチベーションの維持
度重なる怪我により、モチベーションの維持が課題となりましたが、メンタルコーチの助けを借りて「小さな目標設定」を取り入れました。リハビリ中は、歩行から滑走、単発ジャンプ、4Lzの助走までの各フェーズを設定し、それぞれの達成時に達成感を得られるようなプランを実施しました。成功体験を積み重ねることで練習への意欲を保ち、怪我への不安を克服しました。
復帰後のパフォーマンスの向上
復帰後の東日本選手権では、4Lzを70%の成功率で着氷しました。以前よりもジャンプの入りが安定し、稼働域と体幹の制御が改善されたとの評価を受けました。また、怪我前と比べ、無理なエッジ操作を避けたことで技術点(PCS)も向上し、復帰早々に優勝を果たしました。
今後の4Lz習得と長期的な視点
羽生選手は「4Lzは生涯の目標」と語り、リハビリ後も慎重に挑戦を続けています。今後は定期的なMRI検査や動作解析を行い、負荷のかかる動作に迅速に対応できる体制を整える考えです。高齢化が進む中、リスク管理がますます重要になるため、科学的トレーニングを通じて「怪我しない4Lz」の習得を目指しています。
まとめ
羽生結弦選手の4回転ルッツ練習に伴う怪我は、足首捻挫や疲労骨折という大きな試練をもたらしましたが、専門医療チームのサポートや練習メニューの見直し、メンタルケアを通じて見事に復活を遂げました。長期的な視野で怪我予防に取り組みながら、今もなお4Lzへの挑戦を続ける姿勢は、彼の不屈の精神を示しています。
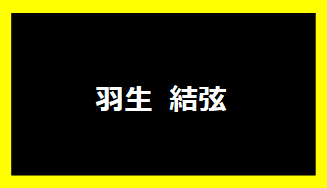
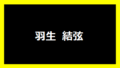
コメント